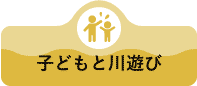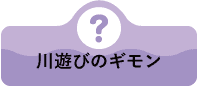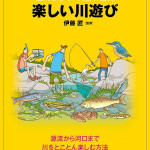我が家はいわゆる大都市の街中にあるので、透き通った水の泳げる様な川は近くにない。ないが、無限に面白い水辺の遊び場はいっぱいある。
今日は新しく淡水エビ水槽を立ち上げようと思ってしまったため、そんな幾つかある遊び場の一つに出かけることにした。
テナガエビ、ミナミテナガエビ、ヒラテテナガエビ、スジエビなど肉食系、ヌマエビ、トゲナシヌマエビ、ミゾレヌマエビ、ミナミヌマエビなどの草食系に大別される淡水エビをきちんと同定できるようになりたいし、もっと詳しく知りたいと思ったからだ。そして何と言っても、エビはかわいい。エビ水槽に入れるシジミ、タニシ、水草も採りたい。

あまり時間がなかったので、ウェーダーなど履かずに手早く済ませたい。新しい水槽を買いに行く時間も欲しい。そこで、車からすぐ降りられる田んぼの用水路に行くことにした。

水量は少なく、遊泳するような魚は棲めない。棲むのはアメリカザリガニ、マドジョウ、ヌマエビ、スジエビ、シジミ、タニシ。新しく水槽を立ち上げる際のベースの生き物はここで簡単に採れるのだ。

この用水路が面白いのは、すぐ横を流れる川では見られない水草が自生してこと。
そして驚きなのは、その川の水温が温水かと思わせる温かさのに比して、用水路の水温がかなり低いことだ。この低水温だから、これらの水草が自生できるのかもしれないが、この少水量でなぜ低水温でいられるのか。周りの田んぼが関係しているのだろうが、確かめることはできなかった。今度はその辺りを解明すべく、踏査してみよう。


前に来た時は用水路の半分ほどがコカナダモに覆われており、残りをエビモとヤナギモとで占めていたのだが、今日見てみると、全体的に水草は少なくなっていた。

しかとは分からないが、水路に沿う畦道にコカナダモが山と積まれていたり、今日もアメリカザリガニが幾匹も干からびたりしているから、外来種駆除に取り組む人がいるのやもしれぬし、ただ用水路の詰まりを掃除しただけかもしれない。
もしそうだとすれば、一面コカナダモに覆われたような水路だから、コカナダモに混じってエビモなども一緒に駆除されてしまったのだろうか。



目的のヌマエビ類、シジミ、タニシを一通り採れたので良しとする。
それぞれの詳しい種別は帰ってからの同定タイムにとっておく。これが楽しいのだ。図鑑と生き物とを矯めつ眇めつ、あーでもないもこーでもないと思索の旅に出る。ヌマエビ類はルーペがないと同定できないからより楽しい。秋の夜長にはぴったりなのだ。
伊藤 匠
★シジミは名古屋市内の川でも採れる★
★ヌマエビを捕るなら岸辺の水草を★